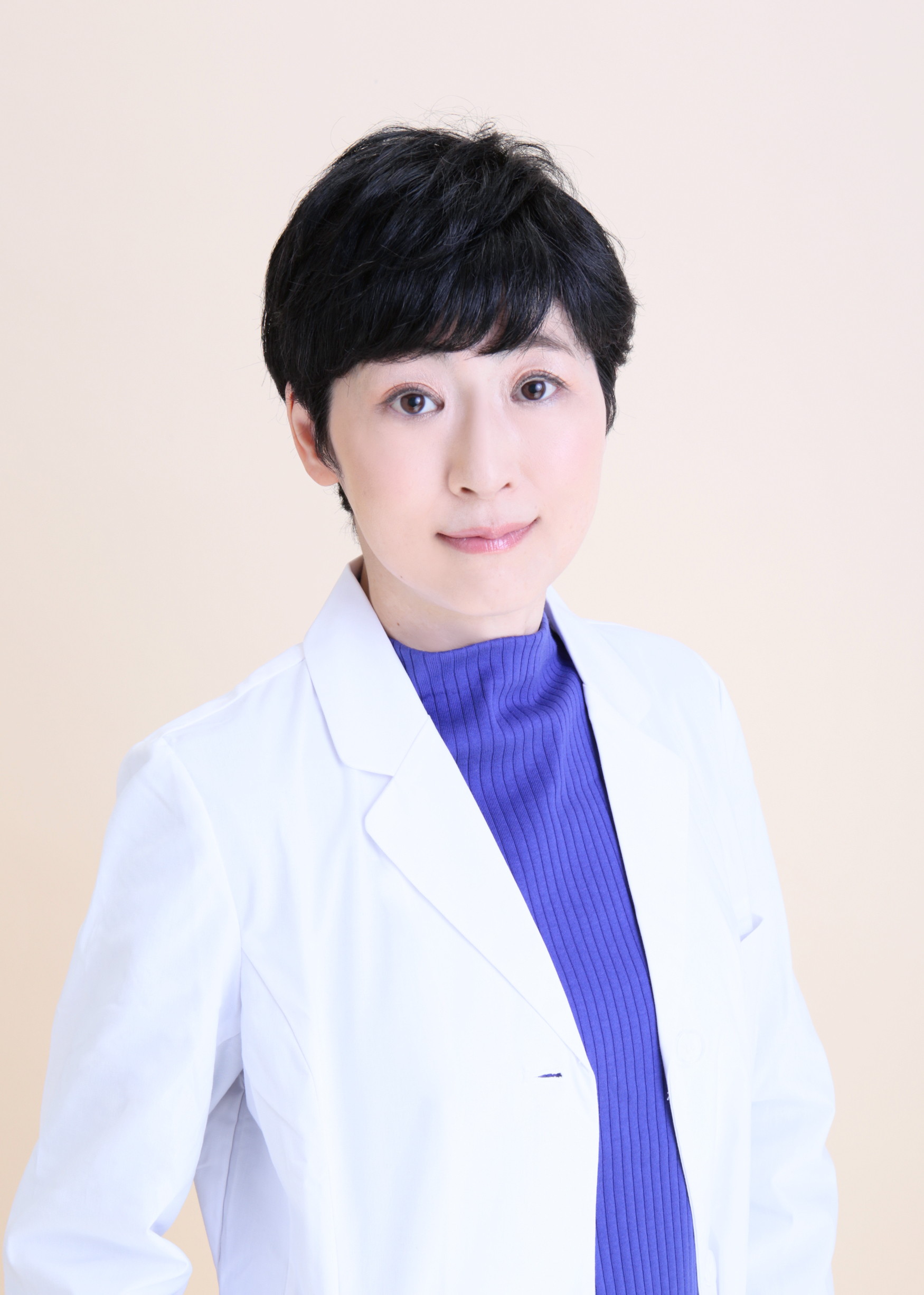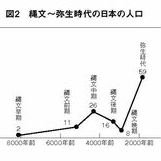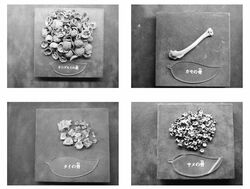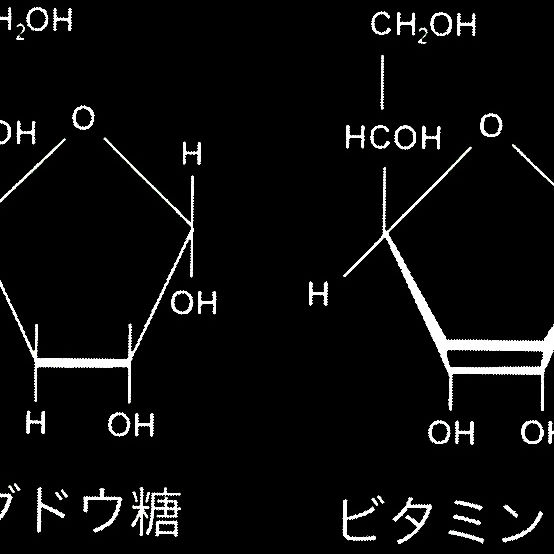糖尿病で亡くなった藤原道長。原因は贅沢三昧の食生活だった?
「蘇」に蜜をかけて食べていたという藤原道長【和食の科学史④】
■呪術が科学だった平安時代
794年、桓武天皇が都を平安京に移し、平安時代が始まります。ここでも施薬院と悲田院が運営され、病人と孤児の世話、薬草の管理、公的な医術教育などが行われました。医師は薬草をはじめとする薬を投与し、鍼(はり)を打ち、灸をすえ、ヒルに血を吸わせるなどの治療をほどこしました。
医薬への関心が高まるなか、京の都では薬草が取り引きされるようになり、984年には日本最古の医学書とされる『医心方(いしんぼう)』が編纂されました。大陸の書物から病気や薬に関する記述を抜き出して解説したもので、白内障の手術に関する記載もあります。図4は平安時代後期の『病草紙(やまいのそうし)』に描かれた手術の様子です。原理は現在と同じで、濁った水晶体を細い針でつついて取り出していました。

しかし、医術には大きな壁がありました。X線検査はもとより血液検査もなかったため、弱っていく人を前にしても、体の中で何が起きているのか見当がつきませんでした。頼りになるのは経験だけで、こういう症状にはこれを食べ、この薬草を使うと効くんじゃないかと手探りで治療して、効果がないとなれば祈祷に頼るしかなかったのです。
当時の人はそれでも医術に信頼を寄せていましたが、その一方で呪術には強大な力があると考え、病気になると医師より先に陰陽師(おんみょうじ)を呼ぶのがつねでした。
陰陽師というと、神秘的な力を持ち、どこからともなくあらわれる謎めいた人物というイメージがあります。しかし実際の陰陽師は、中国大陸で発達した陰陽五行(いんようごぎょう)思想の流れをくみ、占いを行う朝廷の役人でした。陰陽五行説についてはあとで説明しますが、この時代、呪術は気安めではなく、しっかりした理論にもとづく「科学」と考えられていたのです。
患者の枕もとに呼ばれた陰陽師は、病気の原因となっている物(もの)の怪(け)や怨霊の正体を占ったうえで、怨霊をなだめるための祈りを捧げました。
紫式部の手になる『源氏物語』にもさまざまな怨霊が登場します。たたりを起こすのは死者とは限らず、六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)の生霊が源氏の正妻である葵の上に取り憑(つ)いて苦しめる場面は物語のクライマックスの一つです。